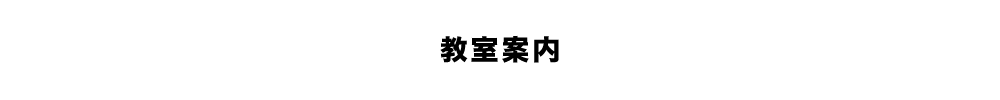2025/9/11
『知識』と『知恵』
▼学びは、決して知識や情報を頭で理解し、記憶するだけではありません。何かの知識を持ってそれを身体を通して感じてみる、つまり身体感覚を伴う体験で「気づき」「腑に落ちる」ということが起きます。
体験を通して、初めて学びは知恵に転化するのです。この自分の身体の体験から起きる学びこそが、私たちの意識を変化させ、人間としての成長と進化をもたらしている源なのです。
▼数学の得意な人と苦手な人、好きな人と嫌いな人の違いの特徴は、以下の点です。
①「考えることができるか、できないか」
②「考えようとするか、しないか」
問題を見て、
③「すぐに分からないと諦めてしまうか、何とか解こうと試行錯誤しながら、考えようとするか、しないか」
▼試行錯誤しながら考え、「考える力」を伸ばし続けたお子様と、そうでないお子様では、年齢が上がるにつれ、数学力の差は目に見えて大きくなってきます。
▼「わかる」と「ひらめく」
数学は勉強をすれば、「解法がわかる」ようになってきます。学校のテストなどでは、頑張って勉強し、解法がわかれば十分に高得点が取れるようになります。
数学の入試問題などの応用問題では、平均点は取れても、「わかる」だけでは高得点はなかなか取れません。
▼壁を突破するためには、「ひらめく」ことが重要になってきます。「ひらめく力」は「考える力」であり、「考える力」を伸ばすためには、「考える習慣」が大切です。
「考える習慣」を身に付け、「考える力」を伸ばしていきましょう。
解説があれば、効率良く「解法がわかる」ようになり、成績も効率良く上げることができます。
▼「従来の暗記重視の教育は良くない、もっと子供たちに考えさせるような授業をするべきだ」という言葉をよく耳にします。なんとなく良い言葉のように聞こえてしまうのですが、私はあまり好きではありません。
▼まず知識を持たなければ、何を思考すれば良いかもわからないし、物事が正しいのか間違っているのかを判断することもできません。
社会人になって、「結局、信用できるのは知識のある人だ」ということを実感する機会も多いです。
「暗記なんて、しょうもない」という言葉に逃げずに、まずは暗記から勉強を始めましょう。