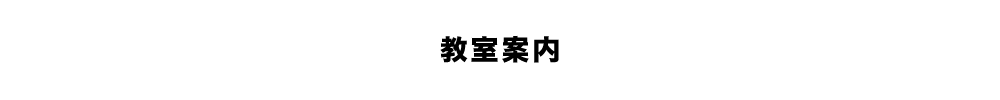ブログ
-

2026/2/25
夢の楽園の「嘘」を剥ぐ:私立中高一貫校、四つの欺瞞
中学受験を勧める側は、私立中高一貫校を「夢の楽園」のように語る。しかし、その内側に踏み込めば、美辞麗句に塗り固められた「四つの欺瞞」が浮かび上がる。
①「塾へ行かなくて良い」という嘘:
独自のカリキュラムで手厚く指導すると謳うが、実態は超高速の先取り教育だ。生徒たちは結局、学校帰りにまた別の塾へ通い詰める二重生活を強いられている。
②「先取りが有利」という嘘:
合格実績は「教育力」ではなく、入学時点で「すでに東大に行ける層」を囲い込んでいるビジネスの成果だ。例えば、開成や渋幕、関西なら灘から現役で東大へ入る生徒は、地元の公立校に進んだとしても、自力で合格を勝ち取る力を持っている。
★事実、大阪周辺の都市部において、かつての『公立進学校が誇っていた東大合格者数の合計』と、現在の『灘などの私立が稼ぎ出す合計数』に大きな違いはないとされる。
もし、エリートの私立中高一貫校の生徒と、公立の生徒を全員入れ替えたなら、その公立校が東大合格者数ナンバーワンになるだけの話なのだ。
③「いじめがない」という嘘:
行儀の良い子が集まるから荒れはないと言われるが、密室化したエリート校の中では、プライドの高い子供同士による執拗ないじめが確実に存在する。名門校の校長ですら、その事実を突きつけられると沈黙を選んでしまう。
④「質が保証されている」という嘘:
これが最大の闇だ。私立校は教育委員会の管轄でも、文科省の直接の指導対象でもない。行政の窓口が担当しているだけで指導権限がないため、トラブルが起きても「やりたい放題、逃げ切り勝ち」がまかり通る構造がある。
◆「私立」「一貫」という看板の安心感に身を委ね、子供をシステムの密室に閉じ込めてはいませんか。
◆その高い壁の内側で、わが子の「尊厳」が誰からも守られないリスクを、あなたは直視できますか。 -
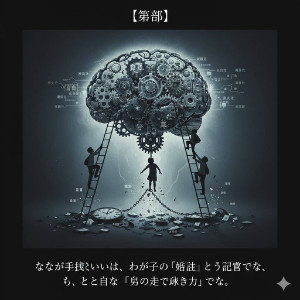
2026/2/25
中学受験という「聖域」の正体
偏差値に、家族の幸せをジャックされていませんか?
①「わが子の将来のため」
中学受験という世界に足を踏み入れた親たちが、共通して掲げる免罪符です。
高額な塾代、深夜までの家庭学習、親子でボロボロになる毎日。本来なら「異常」なはずの光景が、この世界では「頑張る親子の美しい物語」へとすり替えられてしまいます。
でも、一度立ち止まって、その熱狂の渦を外から眺めてみてください。そこにあるのは、親の**「将来への不安」**を燃料にして動く、巨大な装置の姿かもしれません。
②削ぎ落とされる「試行錯誤」という宝物
塾が提示する「偏差値」という物差し。それに従順であることこそが正解だと信じ込む日々の中で、子供たちは大切なものを失っていませんか?
③失敗から学ぶゆとり
「なぜ?」と立ち止まって考える時間
数字には表れない自分自身の価値
効率の名の下に、小学生という多感な時期に経験すべき「寄り道」が容赦なく削ぎ落とされています。成績という数字だけで人間を測る冷徹な視線にさらされ、親は狂奔し、子供は追い詰められていく……。
④「空っぽの優等生」の量産
今、問題になっているのは、合格がゴールになってしまう**「燃え尽き症候群」**です。
指示された通りに動くことには長けていても、いざ中学に入った途端、自ら考える意欲を失ってしまう「空っぽの優等生」を、このシステムは量産し続けてはいないでしょうか。
⑤中学受験は、家族の「尊厳」をかけた実験場
中学受験は、単なる進学の手段ではありません。
偏差値という魔物に飲み込まれず、親が最後まで**「子供の尊厳」**を守り抜けるかを試される、壮大な実験場なのです。
「私立」「一貫校」という看板さえ手に入れば安心ですか?
システムの密室の中で、わが子の心が悲鳴を上げていませんか?
高い壁の内側で、誰からも守られないリスクを直視すること。
今一度、その「聖域」の正体を見つめ直してみませんか。 -

2026/2/24
【小学生・中学生の保護者様へ】塾で伸びる子は「100点」より「質の高いバツ」を持ってくる!
塾に通っている小学生や中学生のお子様を持つ保護者のみなさま、テストの結果を見て「また間違えてる…」とガッカリしていませんか?
実は、その「間違い」こそが、お子様が挑戦している証拠。むしろ「お宝」なんです!
「できる子」と「できない子」の決定的な違い
私が塾で多くの生徒たちを見ていて確信していることがあります。
できる子ほど、よく間違える。
なぜなら、彼らは常に自分の限界の少し先にある問題に挑戦しているからです。
できない子ほど、間違えない。
なぜなら、確実に解ける問題しかやらず、難しいことへの挑戦を避けているからです。 「間違えたくない」という気持ちは、大人も子供も同じですよね。でも、今の世の中は少し世知辛い。正解ばかりが評価され、効率重視で失敗が許されない空気があります。
しかし、勉強の世界だけは別です。塾のノートが真っ黒になるまで試行錯誤し、たくさんの「バツ」を積み重ねること。それこそが、本物の学力を育てる唯一の道なんです。
エジソンが教える「1万通りの失敗」の価値
発明王エジソンは、電球を発明するまでに1万回も失敗したと言われています。しかし、彼は周りから失敗を指摘された際、こう答えました。
私は失敗したことがない。ただ、1万通りの『うまくいかない方法』を見つけただけだ」
算数や数学でも、「この補助線を引いたらダメだった」「この計算順序は遠回りだった」と気づくこと。
それは「できない」のではなく、「一つ賢くなった」ということなんです。小学生や中学生のうちに、この「失敗を恐れない心」を養うことこそ、塾で学ぶ最大の価値と言えるでしょう。
塾の先生から保護者様へのアドバイス
もしお子様が塾から帰ってきて、テストの解答用紙がバツだらけだったら、ぜひこう声をかけてあげてください。
わあ、こんなに難しい問題に挑戦したんだね!すごいワン!」
保護者の方が「バツ」を面白がってくれると、子供たちは安心して間違えることができます。そして、安心して間違えられる子こそが、中学生になって難しい数学や英語にぶつかった時、自力で乗り越えていく力を発揮するのです。
まとめ:先生のつぶやき
効率や経費削減ばかりが叫ばれる世知辛い時代ですが、子供たちの学びは「非効率」でいいんです。
泥臭く、何度も間違えて、それでも「次はこうしてみよう!」と目を輝かせる。そんな挑戦を、私たちは全力で応援していきたいですね。
今日も塾で、エジソンのような「前向きな間違い」に出会えるのを楽しみにしています! -

2026/2/15
捨て問を作れ!合格に100点は不要:戦略的受験のススメ
受験という戦場において、真の勝者は「一番多く解いた人」ではなく、「合格ラインを賢く超えた人」です。
特に中学生の高校入試や、応用力が試される小学生の中学受験において、塾の先生が口を酸っぱくして言うのが「捨て問(すてもん)」の重要性です。
100点を目指すリスクを知る
入試で100点を取ろうと意気込むと、難問に時間とパワーを奪われ、本来正解すべき基礎・基本の問題でケアレスミスを犯したり、時間が足りなくなったりします。
合格には満点はいりません。大切なのは、自分がいま何点必要なのか(7割?60点?)という目標設定です。
志望校の合格ラインが分からなければ、すぐに学校や塾の先生に確認しましょう。
勝利のための「判別」作戦
目標が決まったら、次に行うのは問題の仕分けです。試験開始の合図とともに、まずは全体をさらっと見渡してください。
A層(基礎・基本): 絶対に落とせないサービス問題
B層(標準+α): ここで正解を積み上げればライバルに差をつけられる
C層(難問・奇問): 解かなくていい「捨て問」
この判別ができるようになると、入試において最強の武器になります。
数学で見る「戦略的得点術」
公立高校の数学を例に挙げると、出題形式は毎年ほぼ固定されています。問1の計算問題や、各単元の(ア)(イ)といった基本問題を確実に仕留めるだけで、実は平均点超えの70 点前後を安定して取ることが可能です。
難解な証明の最後の一問や、複雑すぎる立体図形に手を出してパニックになる必要はありません。たとえ新傾向の問題が出ても、それは受験生全員にとって条件は同じ。
合否に直結するのは、誰もが解ける基本問題で「いかにミスをしないか」なのです。
まとめ:ライバルに勝つ唯一の方法
受験で差がつくポイントは、実は「難しい問題が解けるかどうか」ではありません。
「基礎・基本、標準問題で一問も取りこぼさないこと」、これに尽きます。
「この問題は後回し!」と決める勇気が、あなたを第一志望合格へと導きます。 -

2026/2/11
【算数・数学の魔法】「絶対に同じ」を証明する「鳩ノ巣原理」って知ってる?
塾に通う小学生や中学生の皆さんは、「絶対にこうなる!」と自信を持って言えることはありますか?
今日は、ちょっと不思議で面白い「鳩ノ巣原理(はとのすげんり)」のお話です。
①「誕生日が同じ人」は必ずいる?
例えば、塾の教室に400人の生徒が集まったとします。このとき、「誕生日が全く同じペア」は、計算しなくても100%確実に存在します。
なぜなら、1年は最大365日。366人目がいれば、必ず誰かの誕生日と重なりますよね。
これが「鳩ノ巣原理」の基本。箱の数より、中身が多ければ、必ずどこかの箱に2つ以上入るという考え方です。
②東京のどこかに「自分と毛の本数が同じ人」がいる!?
もう少し視野を広げて、中学生レベルの論理で考えてみましょう。
人間の髪の毛は多くて15万本。対して、東京の人口は1,400万人です。
「0本〜15万本」という「毛の本数の箱」を用意して、都民全員を振り分けていくと……?
そう、計算上、同じ本数の人があちこちに大量発生します。会ったこともない誰かと、毛の本数で繋がっているなんて、ちょっとワクワクしませんか?
③暗闇で靴下を選ぶには?(思考力のトレーニング)
最後に、皆さんの思考力を試すクイズです。
引き出しの中に「黒・白・青」の3種類の靴下がバラバラに入っています。目をつぶって、最低何枚取り出せば、確実に「同じ色のペア」が作れるでしょうか?
「色(箱)」が3つあるので、4枚(鳩)取り出せば、必ずどれか1色が揃います。
まとめ:思考力の種をまこう
「鳩ノ巣原理」は一見当たり前のように見えますが、実は高度な数学やコンピュータの世界でも使われる重要な考え方です。
**「なぜそうなるのか?」**という一歩先の理屈を考える癖をつけることが、算数や数学、そして将来の解決力を鍛える第一歩になります。
塾での勉強も、この「当たり前の中にある不思議」を見つける楽しさを知れば、もっとワクワクするものに変わりますよ!