サクシードブログ
Homeブログ
-

2026/2/11
【算数・数学の魔法】「絶対に同じ」を証明する「鳩ノ巣原理」って知ってる?
塾に通う小学生や中学生の皆さんは、「絶対にこうなる!」と自信を持って言えることはありますか?
今日は、ちょっと不思議で面白い「鳩ノ巣原理(はとのすげんり)」のお話です。
①「誕生日が同じ人」は必ずいる?
例えば、塾の教室に400人の生徒が集まったとします。このとき、「誕生日が全く同じペア」は、計算しなくても100%確実に存在します。
なぜなら、1年は最大365日。366人目がいれば、必ず誰かの誕生日と重なりますよね。
これが「鳩ノ巣原理」の基本。箱の数より、中身が多ければ、必ずどこかの箱に2つ以上入るという考え方です。
②東京のどこかに「自分と毛の本数が同じ人」がいる!?
もう少し視野を広げて、中学生レベルの論理で考えてみましょう。
人間の髪の毛は多くて15万本。対して、東京の人口は1,400万人です。
「0本〜15万本」という「毛の本数の箱」を用意して、都民全員を振り分けていくと……?
そう、計算上、同じ本数の人があちこちに大量発生します。会ったこともない誰かと、毛の本数で繋がっているなんて、ちょっとワクワクしませんか?
③暗闇で靴下を選ぶには?(思考力のトレーニング)
最後に、皆さんの思考力を試すクイズです。
引き出しの中に「黒・白・青」の3種類の靴下がバラバラに入っています。目をつぶって、最低何枚取り出せば、確実に「同じ色のペア」が作れるでしょうか?
「色(箱)」が3つあるので、4枚(鳩)取り出せば、必ずどれか1色が揃います。
まとめ:思考力の種をまこう
「鳩ノ巣原理」は一見当たり前のように見えますが、実は高度な数学やコンピュータの世界でも使われる重要な考え方です。
**「なぜそうなるのか?」**という一歩先の理屈を考える癖をつけることが、算数や数学、そして将来の解決力を鍛える第一歩になります。
塾での勉強も、この「当たり前の中にある不思議」を見つける楽しさを知れば、もっとワクワクするものに変わりますよ! -

2026/2/9
不思議な「背理法」の世界「ありえない!」から真実が見える?
**今日は、数学の探偵術**「背理法」**のお話です。「もし〜だったら矛盾しちゃうよね」と追い詰めて、正しい答えを導き出す面白い考え方なんですよ。中学生のみなさん、ついてきてくださいね。
1. 「√3 + 5」は無理数?
√3 がバラバラな数字が続く「無理数」なのは有名ですが、それに「5」を足した数もやっぱり無理数なんです。
もし「√3} + 5 が有理数(分数)」だったら? と仮定します。
その数を有理数 r とすると、√3 + 5 =r です。
5を移動させると、.√3 = r - 5 になります。
【矛盾!】 有理数 r から 有理数5 を引いても「有理数」のはず。
なのに左側は「無理数」の √3 。無理数=有理数なんてありえません!
だから、√3 + 5 は無理数で決まりです。
2.素数(2, 3, 5, 7...)の数は無限にあります。宇宙の果てまで続いています。
「素数は有限しかない」と仮定すると矛盾が起きることを利用して、逆の結論を導き出す**「背理法(はいりほう)」**という手法を使って証明します。
①最初に「ウソの仮定」を立てる
まず、**「素数はリスト(2, 3, 5, ……, 最後の一番大きい素数)にある分だけで全部だ!」**というウソのルールを決めます。この時点では、世界にはリストに載っている素数しか存在しないことになります。
②特別な数「M」を作る
リストにあるすべての素数を掛け合わせて、最後に「1」を足した大きな数「M」を作ります。
M =(2 × 3 × 5 × …… × 最後の一番大きい素数)+ 1
③Mを素数で割ってみる
作った数「M」を、リストにあるどの素数で割ってみても、最後に足した「1」のせいで必ず「1」余ってしまいます。「割り切れる素数がリストの中に一つもない」という事態が発生します。
④ここであり得ないこと(矛盾)が起きる
どんな数も「必ず素数で割り切れる」はずなのに、リストの素数ではどれも割り切れません。
この矛盾が起きた原因は、最初に立てた「素数は有限だ」という仮定が間違っていたからです。
パターンA: M自体が、リストの外側にある「新しい素数」だった。
パターンB: リストに載っていない「未知の素数」で割り切れた。
⑤結 論
どちらに転んでも、最初に決めた「リストがすべてだ」という前提がウソだったと証明されます。
したがって、**「素数は無限にある」**ということが導き出されるわけです。
3.パーティで「知り合いの数」が同じペアが存在する。
①仮定(定理の否定) 「5人の集まりにおいて、全員の知り合いの数がバラバラである」と仮定します。
②知り合いの数の範囲を特定する 5人の集まりにおいて、ある一人が持ちうる「知り合いの数」の候補は、最小で0人(誰も知らない)、最大で4人(自分以外の全員を知っている)の 0, 1, 2, 3, 4 の5通りです。
③矛盾を導き出す(ここがポイント!) 仮定より「5人全員の知り合いの数が異なる」とするなら、5人に対して5通りの数値(0, 1, 2, 3, 4)が1つずつ割り当てられるはずです。つまり、このグループには必ず以下の二人が存在することになります。
Aさん: 知り合いが 0人(誰も知らない)
Bさん: 知り合いが 4人(自分以外の全員を知っている)
しかし、これは論理的に破綻しています。
なぜなら、Bさんが全員を知っているなら、その「全員」の中にはAさんも含まれるため、AさんにはBさんという知り合いが少なくとも1人存在しなければならないからです。
したがって、「0人」と「4人」は同じ世界に同時には存在できません。
④鳩の巣原理(引き出し論法)への着地 「0人」と「4人」が共存できない以上、5人が取りうる知り合いの数のパターンは、以下のいずれかのグループに限定されます。
グループ ア:{0, 1, 2, 3} の4種類
グループ イ:{1, 2, 3, 4} の4種類
いずれの場合も、「5人(鳩)」に対して「4種類の数(巣)」しかありません。
⑤結論 鳩の巣原理により、5人を4つの分類に振り分けると、必ず少なくとも2人は同じ数値の箱に入ることになります。 よって、「全員の知り合いの数が異なる」という最初の仮定は誤りであり、**「知り合いの数が同じペアが必ず存在する」**ことが証明されました。
★鳩の巣原理: n 個の巣に、n+1 羽の鳩がいたら、どこかの巣は2羽以上になりますよね。
知り合いのパターン: n 人のパーティで、一人の知り合いの数は「0人」〜「n-1人」の計 n 通り。
【矛盾!】 でも、同じ場所に「誰も知らない人(0人)」と「全員知っている人(n-1人)」は同時には存在できません。
つまり、実質のパターンは n-1 通りしかありません。
結論: n 人を n-1 個のパターンに分けるので、必ず同じ数の知り合いを持つ人が出てくるのです。
独り言:
「絶対にそうならない」という矛盾を見つけることで、正しい道が見えてくる。なんだか人生のヒントにもなりそうですね! -

2026/2/4
★高校数学への招待状★思考の「ひっくり返し」で世界が変わる?
受験シーズンもいよいよ佳境。
塾の教室で、必死に机に向かう中学生の皆さんの背中には、私たち講師も胸が熱くなります。
特に、中学3年生で入塾した生徒さんたちが、驚異的な追い込みで見せる「最後の伸び」は、本当にお見事です!
そんな皆さんが志望校を突破したあと、高校数学で最初に出会う「論理のパズル」を少しだけ先取りしてお話ししましょう。
1. 視点を変える「対偶(たいぐう)」の技
「数学が面白いなら、成績は上がる」という言葉、これと全く同じ意味を保ったまま、文章を裏返すのが「対偶」です。
「成績が上がらないなら、数学は面白くない(はずだ)」正面から証明するのが難しいとき、あえて裏口に回って正しさを証明する。賢い「言い換え」の技ですね。
2. あえて間違えて見せる「背理法(はいりほう)」
もう一つ、高校数学の真骨頂が「背理法」です。あえてウソの仮定をして、自爆を誘うドラマチックな証明術です。
√2の正体:左右で「因数の個数」が合わない!
例えば、**「√2 は無理数である」**ことを証明するために、あえて逆に**「√2 は有理数だ!(分数表示できる)」**と、
あり得ないウソの仮定をしてみます。
すると、これ以上約分できない分数(既約分数)として、次のように書くことができます。
「√2が分数(b/a)だ!」と仮定して「√2=b/a」、両辺にaをかけて√2a=b
二乗して、式を整理すると、こうなります。
2 × a^2 = b^2 (a^2は、aの二乗・・a×a、 b^2は、bの二乗・・b×b)
この式の左側と右側で、含まれている「因数の総数」を数え比べると、一瞬で矛盾がわかります。
右側(b^2)の因数の個数は、絶対に【偶数個】
bという数字が何であっても、それを2乗(b × b)すれば、そこに含まれる因数の個数は必ずペアになります。
2乗された数字の因数の数は、**理屈抜きで絶対に「偶数個」**です。
左側(2 × a^2)の因数の個数は、絶対に【奇数個】
a^2 の部分も、同じルールで因数の個数は「偶数個」になります。
ところが、その外側に**「2」という因数がもう1つ**掛け算されています。
「偶数個 + 1個」になるので、**左側にある因数の総数は、絶対に「奇数個」**になってしまいます。
結論:右と左で「数」が合わない!ワン
「左は奇数個、右は偶数個。イコールで結ばれているのに、因数の総数が違うなんて絶対におかしい!」
この**「個数の不一致」**こそが、√2が分数ではない(無理数である)という決定的な証拠です。
最後にこうした論理の美しさに触れると、数学は単なる計算ではなく、**「正しく考えるための武器」**だと気づきます。
小学生からコツコツ頑張ってきた子も、中3で一気にスパートをかけた子も、高校という新しい舞台では、ぜひ「知的な遊び心」を持って学んでほしいと願っています。
サクシードでの学びは、人生の通過点。でも、ここで培った「論理的に答えを導く力」は、一生モノの宝物になるはずです! -

2026/2/1
塾屋の「危機感」に踊らされていませんか?
先日、ある学習塾の元担当者と話す機会がありました。彼は短期間で小学生・中学生の生徒数を倍増させた実績の持ち主ですが、その手法は実に巧妙です。
まず中学受験を控えた小学生に、平均30点ほどの極めて難しいテストを受けさせ、親には「学校の勉強だけでは通用しない」と不安を植え付けます。
その裏で楽しい理科実験を見せて親を安心させ、最後に「30点」という現実を突きつける。
不安と安心のギャップで「学習診断」へと誘導し、そのまま入会させる……。まさに**「危機感を煽れば、塾屋が儲かる」**という構図です。
しかし、本来の教育とは、あるいは地域に根ざした塾の役割とは「不安を解消するために通うもの」であってはいけないはずです。
私が理想とするのは、**「エラーを恐れて届きそうな球だけを待つ」生徒ではなく、「エラーしてもいいから、届きそうにない球に必死で飛びつく」**生徒を育てることです。
小学生のうちからバッターボックスで「見逃し三振」をして立ち尽くす癖がついてしまうと、中学生になって勉強の難易度が上がったときに、挑戦すること自体を諦めてしまいます。たとえ「空振り三振」に終わっても、全力でバットを振る経験の方が、次への成長に確実に繋がります。なぜなら、その空振りの軌道こそが、自分の限界を知り、新しい技術を身につけるための「自分だけのデータ」になるからです。
こうした**「自分から飛びつく勇気」**を育むために、私たち塾講師に求められるのは、生徒との適切な距離感です。 依存させすぎては自立の芽を摘み、突き放しすぎては不安で動けなくなってしまいます。
小学生、中学生という多感な時期に、生徒が失敗を恐れずに思考のキャンバスへ「大きな図」をフリーハンドで描き、自分の目で見て、手を動かして試行錯誤できる。
そんな「心の安全基地」のような環境を守ることが私たちの使命です。 -
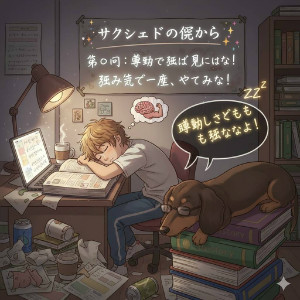
2026/1/27
【生徒たちへ】勉強で死んだ人はいない!死ぬ気で一度、やってみな!
「先生、勉強しすぎて死んじゃうよ~」なんて冗談を言う子がたまにいますが、私は毎年、塾に来る中学生や小学生たちにこう断言しています。
「大丈夫、日本で勉強しすぎて死んだ人は一人もいないから。安心して死ぬ気でやりなさい!」と。
気になって調べてみたのですが、日本では本当にいないようです。
昔の中国の「科挙」という試験では、あまりの過酷さに命を落とす人もいたようですが、現代の日本の受験はそこまでではありません。三日間閉じ込められるわけでも、落ちて命を取られるわけでもない。
たかだか数ヶ月、数年間の挑戦です。
人生を変えるのは「心のスイッチ」
「たった一年の勉強で人生が変わるの?」と思うかもしれません。 でも、部活を引退した夏から猛勉強して第一志望に合格した先輩や、コツコツ朝練を続けてレギュラーを掴んだ仲間を思い出してください。
「やるぞ!」と決めて継続すること。これだけで、運命は動き出します。
私の好きな言葉があります。
①心が変われば、態度が変わる。
②態度が変われば、行動が変わる。
③行動が変われば、習慣が変わる。
④習慣が変われば、人格が変わる。
⑤人格が変われば、運命が変わる。
⑥運命が変われば、人生が変わる。
すべては自分の「意志」一つで、未来はいくらでも塗り替えられるのです。
「習慣」という最強の武器を手に入れる。
とはいえ、コツコツ続けるのは並大抵のことではありません。 コツは、無理のない作業から習慣化すること。
「朝起きたら、まず机につく」。 勉強しなくてもいい、ただ座るだけ。 これを繰り返すだけで、体は自然と「勉強モード」を覚えていきます。
もし、自分に何が足りないのか、どう進めばいいのか分からなくなった時は、知識のある人――つまり、私たち塾の先生を頼ってください。 足りないものを補うステップさえ見えれば、あとは進むだけです。
行きたい学校があるなら、四の五の言わず、一度「死ぬ気で」向き合ってみませんか。
大丈夫、死にゃしないから。 その一歩の先に、見たこともない新しい自分の人生が待っていますよ!