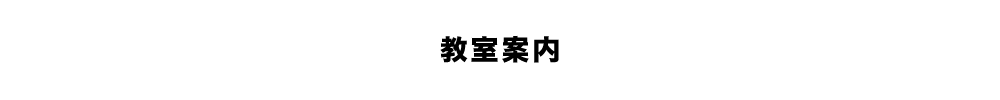ブログ
-

2025/8/12
なぜ勉強するのか?~無知であると損をする~
「勉強をしないと、無知で損をする。」
有名な漫画「ドラゴン桜」でも語られている論理です。
ドラゴン桜の論理
「お前らこのままだと、一生騙され続けるぞ。社会にはルールがある。その上で生きて行かなきゃならない。
そのルールってやつは、全て頭の良い奴がつくってる。
つまりどういうことか。そのルールは全て、頭の良い奴に都合のいいようにつくられてるってことだ。
逆に、都合の悪い所は わからないように上手く隠してある。だが、ルールに従う者の中でも、賢い奴は そのルールを上手く利用する。例えば、税金。年金。保険。医療制度。給与システム。
みんな、頭の良い奴がわざと分かり難くして、ろくに調べもしない頭の悪い奴らから多く取ろうという仕組みにしている。
つまり、お前らみたいに、頭を使わず、面倒臭がってばかりいる奴らは、一生騙されて高い金払わされ続ける。
賢い奴は、騙されずに得して勝つ。バカは騙されて損して負け続ける。
これが、今の世の中の仕組みだ。だったら騙されたくなかったら、損して負けたくなかったら、お前ら、勉強しろ!」講談社 – ドラゴン桜
初めて聞いた時は「なるほどなぁ」と思いました。
身近に潜む”お金を失う罠”の例
●宝くじ(確率的には買った時点でお金を半分以上失うギャンブル)
●消費者金融(えげつない金利の借金)
●リボ払い(えげつない金利の借金) …何より「怖い」と思うのは、ここらへんのヤバイものが堂々とキャッチーなCMで宣伝されているところですかね…。
知識は力なり さらに、“無知“で損をするのは、お金だけではありません。
時には、命も危険に晒します。
(TVインタビューで「津波に乗ってみたい」と答えていたサーファーがいたことに対して)
もし、海岸に居て大きな地震があったら、すぐ高台に上がらないといけないんですよ。 ~(中略)~
知識があれば助かるわけですね。
このことを「知識は力なり」って言います。フランシス・ベーコン、イギリスの哲学者の言葉ですけど。
僕は地球科学を教えていて「知識は力なり」っていうことを、そのサーファーの女の子に伝えたい。皆さんにも伝えたい。日本国民全員に伝えたい。つまり、やっぱりこれが学問のベースだと思うんですよ。鎌田 浩毅 地球科学者。京都大学名誉教授
さて、保護者の皆さんはどう思いますか? -

2025/8/10
中学進学準備!入学までにすべきこと(国語・算数)
算数:「分数」と「文章題」を復習
中学校の数学では「数学と日常生活を結び付けた文章問題」が積極的に取り入れられています。
そのため、中学入学までに「文章題」をしっかりと復習し、言葉の中から必要な情報を正しく抽出する練習、いわゆる「読解力」を磨くことをおすすめします。
さらに、中学校の数学では、小数よりも分数の計算が頻繁に出題されます。中学入学までに分数の計算問題を見なおして、速く、正確に解けるように復習し、分数に慣れておくことが大切です
整数の計算と遜色ないほどに分数の計算が得意になれば、中学校の数学にも柔軟に対応できるようになるでしょう。
国語:「漢字力」を強化
国語の基本は、文章を読み、その内容を正しく理解することです。そのためには、語彙力が必要になります。さらにその語彙力を鍛えるには、漢字の読み書きができることが重要です。
正しい読み書きに加えて、一つひとつの漢字の意味の理解を深めて語感を磨く訓練を継続していると、国語だけでなくほかの教科の理解度にも必ず好影響が出てきます。
また、中学校になると、必ず漢字で解答しなければいけない問題が多く出題されます。このような問題は正しい漢字を書けないと不正解となりますので、小学生のうちから少しずつ、漢字力を鍛えておくことが大切です。小学校、特に高学年で習った漢字はドリルなどを使って、おさらいをしておきましょう。
わからない言葉と出会うたびに、「辞書で調べる」のを習慣づけるという学習方法を取り入れるのも、語彙力強化に効果的です。勉強中だけでなく、読書やテレビ視聴などの日常生活の中でも、意味がわからない単語などを見つけたら辞書で調べる、ということを繰り返しましょう。
漢字や語彙は何度も接することで使い方を自分の中でかみ砕き、徐々に操れるようになっていくものです。裏を返せば一朝一夕には身につきにくい力とも言えます。小学生のうちから地道に取り組むことが将来の学力底上げにつながるので、コツコツと続けていきましょう。
★算数は計算力。国語は漢字力。~ですね。 -

2025/8/1
効率のいい勉強法
音読勉強法
どれだけ普段は意欲がある人でも疲れが溜まるなどして「どうしても今日は勉強のやる気が起こらない」という日もあるでしょう。
そんな日に試してほしい勉強法が、「音読勉強法」です。
やる気が起こらなくても、とりあえず学習内容を声に出して音読してみるのです。声を発することで脳が刺激され、やる気が引き出されて「よし、勉強しよう」という気持ちになれます。
文章録音勉強法
音読勉強法をさらなる効率的な勉強法に変えられるのが、「文章録音勉強法」。音読勉強法の延長線上にある勉強法と言えるでしょう。
テキストの内容をまず音読してそれを録音し、隙間時間に録音した内容を聞いて学習するものです。
やる気の出ない日の勉強のスタートとして、テキスト1ページ分を音読し、それを録音する(5分程度)その録音内容を、通勤通学の移動時間などを利用して、ヘッドフォンなどで聞いて学習する。
もし理解力が上がってきたら、自分の言葉で解説した内容を録音するのもおすすめです。つまり、自分専用のオーディオテキストを作成するようなイメージです。声に出すことでアウトプットの場にもなるので、さらなる理解力向上につながります。
教科書7回読み勉強法
東京大学法学部を首席で卒業し、現在は弁護士として活動する山口真由さんの勉強法です。この勉強法の基本はその名の通り、「教科書を7回読む」もの。
1〜3回目は、教科書の内容を読み、出題範囲を把握する作業。そして4〜7回目は、「教科書のここにこの内容が書かれている」のを確認する作業です。
理解度は3回目までほぼ横ばいです。しかし4回目から急に理解度が上昇し、7回目に到達する頃には、細かい部分まで理解できるのだといいます。
この勉強法に適しているのは、社会・英語・理科などの、暗記を必要とする教科です。 ミニマム勉強法 「仕事の関係で、急に資格の勉強をしなければならなくなった」「試験まで1ヶ月もない」そんな場合におすすめしたのが、この「ミニマム勉強法」です。
ミニマム勉強法のポイントは以下3つ。
使う問題集は1冊のみ
問題を解く前に解答を読む
必要箇所だけテキストを読む
出題範囲の膨大な資格勉強の場合、問題集1冊でもかなり分厚くなるでしょう。分厚いテキストを見るだけで、「あと1ヶ月で終わるはずない」とモチベーションが下がってしまいます。
そのような場合は、単元や科目ごとに問題集を裁断してしまうのもおすすめ。一つ一つを切り分ければ、厚みが軽減され、勉強に向かうモチベーションを保てます。
そして問題集を解く際は、解答を見ながら問題を解いていきます。
そして、以下の3つで問題に印をつけていくのです。
①問題を読むだけで解けた…●
②解説を読んだので次から自分で解ける…●
③解答を見ないと解けなかった…○
上記のように印をつけて繰り返し○の問題を解き、自分で解けるようになったら○を塗りつぶし●にしていきます。
また○(解答を読まないと解けない)と判断した問題は、テキストを読んで理解を深めます。
★五感をフルに使うことは、大切ですね。 -

2025/7/29
特珠算は塾の金づる
中学受験で特殊算は特に必要ありません。塾に行かなければ特珠算は小学校で習いません。
(中学然りで、ある有名難関中学では、数学授業の初っ端なに、今まで受験で習った算数の解き方すべて忘れて下さい、と言われる)
当然、中学受験で特珠算を知らなくても、高校、大学と進むに何ら問題はない。
それを、小学生にはと延々、バカみたいな時間をかけてこの特珠算を教える。たとえば面積図、比、あまたの線分図・・等々。こんなの負の考え方さえ、きちんと教えればすべて方程式で解いていい。
(別に中学受験の算数のすべてが方程式で解ける、と言ってるわけじゃない。むしろ難関校レベルの出題は方程式で解けるような、簡単な問題はまず出ません)
言いたいことは、子供の貴重な学習時間をいかにこの特珠算を覚えさせるために費やしているかということです。
これなら方程式を教えた方がどれだけ効率的かわかりません。
この馬鹿げた特珠算をネタに、どうだ親は教えられないだろう、だから塾じゃないとだめなんだと。(これで親は塾のいいお客さんになって大金を貢いでいるのです)
(負の数の理解を含めて)方程式の指導なんぞ、塾の馬鹿げた膨大な特殊算指導時間からみたらどの親も容易に教えられるはずです。
★先の見えないこの不安な世情、こんなくだらない山ほどの特殊算、撲滅運動を起こしたい。
もういい加減、小学校教育も(英語教育の導入・プログラミングもいいけど)、この雨後のタケノコのように乱立する親の脛をかじって離さない塾業界をのさばらさないため、小学校算数教育課程の革新を図って欲しいものです。
特殊算は頭脳の発達に役立つなんて投稿はやめて欲しい。
こんな解法できる、できない、言い換えれば中学受験で通塾した、しなかったで人間の価値(高校、大学と)差がないことは明瞭ですから。
画像は、蒲生田岬です。 -

2025/7/16
“学び”の本当の意味と大切さ
みなさんは、授業を受けるとき、どんな気持ちでのぞんでいますか?
「ちゃんと聞いてるよ!」という人もいれば、「早く終わらないかな…」と思っている人もいるかもしれませんね。でも、同じ時間、同じ授業を受けていても、「どんな気持ちで学ぶか」によって、得られるものは大きく変わるんです。
「知りたい」「分かりたい」と思いながら授業を受けると、頭の中でいろんなことがつながって、もっと深く理解できます。逆に、「めんどくさいな」と思っていると、大切なことも耳に入らなくなってしまいます。
たとえ難しい内容でも、「できるかな?」「やってみよう!」と思うことが、学びの第一歩になります。挑戦する気持ちがあると、失敗も経験になり、成長につながっていくのです。学ぶことは、じぶんの未来をつくること。知ること、考えること、チャレンジすることは、全部じぶんの力になります。
これからも、「知りたい」「やってみたい」という気持ちを大切にしてくださいね。どんなことでも、あなたの学びにつながっています!
そして、学ぶってけっこうおもしろい!って思えるようになったら、それはもう、あなたが一歩前に進んでいる証拠です。
~ところで~中学受験問題のはらむ「気持ち悪さ」
中学受験の入試問題には明らかに中学・高校の範囲が出ています。
国語は、もはや漢字さえ小学校の範囲を逸脱していなければいいとばかりに、大学受験生が読むような文章が出るのは当たり前。
理科は、注釈付きながら「硫酸銅五水和物」「浸透圧」などが出るのは当たり前。
社会は、すみません専門外なので省略(汗)。
そして、算数。
明らかに方程式で解いた方が楽でスマートな問題を、無理やりアクロバティックに代数を使わず解く問題ばかり。
「はたしてこれでいいのか?学びが嫌いにならないか?」と疑問に思い始めています。
一種の気持ち悪さ。
高校現代文・高校化学・高校物理・高校数学レベルを出しておきながら「いえいえ、小学生でも解けるはず、なぜなら方程式を使っていないから(一応)文科省の学習指導要領は逸脱していませんよ」というアリバイ作りを見ているような気がする。
私は、いま、切に願っています。
どこかの私立中学が「私立なんですから、何を出そうと自由。うちは『方程式』『ルート』『高校化学・物理』を出しますよ」と、腹をくくって出題してほしい、と。